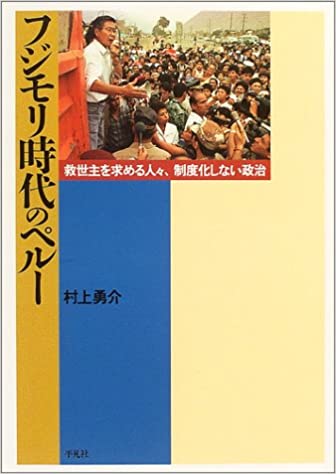書評:フジモリ時代のペルー ~救世主を求める人々、制度化しない政治~
2022年7月24日著者:村上 勇介
出版社 : 平凡社
発売日 : 2004年8月25日
単行本 : 586ページ
☆☆☆ 一読の価値あり
アルベルト・フジモリ氏はペルーの元大統領です。
娘のケイコ・フジモリ氏は先ごろも自身3度目となる大統領選挙選挙に立候補、僅差で敗れています。
父フジモリ氏(以降フジモリ)は1990年~2000年の間、ペルーの大統領に在職していました。本書はその間のペルー政治を分析した学術書です。
確かに学術書ではあり、それに十二分に値する精度と客観性の高い内容と体裁を備えていますが、同時に良質のノンフィクション作品と言ってよい生き生きとした叙述がなされ、著者の力量が窺われます。
フジモリ大統領在職時の20世紀の終盤といえば日本では首相が8人も入れ替わり、自民党が下野するなど、政治的には不安定な時期でした。
その間フジモリは大統領として辣腕を発揮し、中でも日本大使公邸人質事件の解決は日本メディアに大きく取り上げられ称賛を浴びました。
当時筆者も「いっそ日本もフジモリさんに首相を兼ねてもらえばいいじゃん」と冗談を飛ばした記憶があります。
最終的にフジモリは大統領としての支持を失い、訪日中に本国ペルーで大統領から罷免され、帰国後は逮捕されるに至ります。(現在は恩赦をうけてペルーに住んでいるようです)
こうしたフジモリの栄光と転落の過程で、当初は「日系人大統領誕生!」ともてはやした日本メディアの報道も次第に先細りとなっていきましたが、それでもフジモリに対し日本社会は(憶えている人は、という意味ですが)比較的好意的なイメージを持ち続けているように思います。
本書は、そんなフジモリの「偶像」を冷徹に分析しています。
著者はペルー社会の政治や民主主義についての特徴として、強力なリーダーを核とする親分子分関係が重視され、同時に短期的な政治的成果が求められるため、ともすれば民主的な手続きを無視した権威主義的な政治手法が広く認められてきた結果、いわゆる民主主義的な価値観に立脚した経験の積み重ねや、その上での制度の確立がなされてこなかったとしています。
国民も為政者に対し目先の社会課題の解決を最優先に期待し、そのプロセスにおいて必ずしも民主的な手続き(憲法の順守など)がなされなくても頓着しない傾向があります。
こうした「制度化しない政治」や「人民投票的政治意識」がペルー社会の歴史的な構造で、フジモリ政権の政治手法もそれを克服することができなかったと限界を指摘しています。
政権の前半では経済危機の克服やテロの撲滅に成功し、「目先の課題」を解決したことで支持を高め、1992年に「憲法停止措置」という少なくとも日本では考えられない「非民主的」な挙に出て権力基盤の維持強化を図りましたが、これも国民に受け入れられています。
しかし、政権後半になると国際的な通貨危機などの影響もあり経済は伸び悩み、貧困や雇用といった「次なる課題」を解決できなかった結果、支持率は反落してしまいます。
併せて特定の側近に依存し過ぎ、その側近(モンテシノス)の汚職スキャンダルが命取りとなって政権を追われます。
著者はこうしたプロセスを「独立以降のペルーにおいて展開した政治の歴史的、構造的な特徴を反映」したものと捉えています。
日系人大統領フジモリもペルーの歴史的コンテクストの中に生きた大統領であったと。
このようなペルーの政治的伝統や民主主義観は、日本のそれとは随分かけ離れたものとも感じられますが、ラテンアメリカやアフリカ、アジアの一部などの国々では多かれ少なかれ従来よりみられる傾向のように感じますし、欧州や米国で跳梁しつつあるポピュリズムの温床も、目先の利益導入や課題解決を優先してプロセスの民主主義を軽視する「人民投票的政治意識」にあると筆者は考えます。
つまり、20世紀を通じて世界に広められようとされてきた「西欧的自由主義的民主主義」は結局「グローバルスタンダード」とはなり得ず、それどころかその本家本元の欧州/米国でもそれに逆行する動きが市民権を得つつある、ということではないでしょうか?
本書が扱った世紀末とその後の世界の動きを見ているとそのように感じざるを得ません。
(この稿おわり)
【ユニカイブの関連記事】
書評 ベネズエラ
書評 分断のアメリカ

こんにちはHill Andonです。日本語で書くと昼行燈と申します。
サイトオーナー兼管理人兼編集長兼メインライターです。
中小企業のみなさん向けに、エグゼクティブコーチング・経営改善支援・補助金申請支援などを行なっている、フリーランスの経営コンサルタント。中小企業庁の「認定経営革新等支援機関」でもあります。
よろしくお願いします。